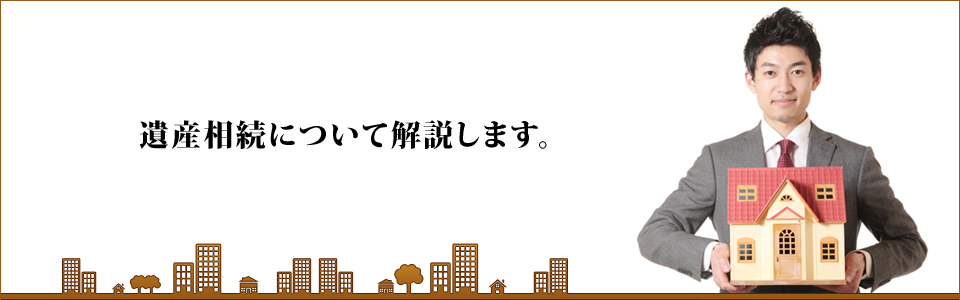
遺言書の書式や遺産相続
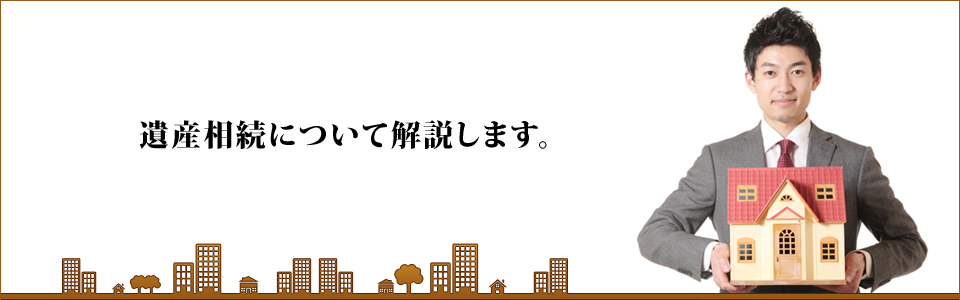
遺留分とは
民法には、法定相続分の規定が明文化されていますが、被相続人が、遺言書を作成して、法定相続人以外の者(例えば愛人)に全財産を遺贈することもできます。
しかし、そのような事態が起これば、残された家族は、住んでいる家の他、全ての財産を失う可能性があり、生活に困窮することも考えられます。このような被相続人の身勝手とも言える遺言の全てをそのまま実行することは、あまりにも相続人に不利益な事態を及ぼすと言わざるを得ません。
そこで民法には、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん) という制度を設けています。
遺留分が保障される相続人の範囲は、配偶者、子、父母であり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分として請求できるのは、配偶者と子が、相続財産の2分の1、また法定相続人が被相続人の親だけの場合は、相続財産の3分の1の範囲です。
ただ、この相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは各相続人の自由意思に任されていて、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害しているとされた者(受遺者や特別受益者等)は、侵害しているとされる遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還する必要があり、その返還する額をめぐって争いになる事例が数多く見受けられます。
そこで、このような争いや訴訟を未然に防止するためにも、遺留分を考慮した遺言を作成することが重要と言えます。
また、遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間と言う短期間の消滅時効にかかります。
また、相続開始から10年間を経過し後に相続があったことを知り、また、その時点で減殺すべき贈与や遺贈があったことを知っても、相続開始から10年以上経過しているので、遺留分減殺請求権の行使はできません。
しかし、そのような事態が起これば、残された家族は、住んでいる家の他、全ての財産を失う可能性があり、生活に困窮することも考えられます。このような被相続人の身勝手とも言える遺言の全てをそのまま実行することは、あまりにも相続人に不利益な事態を及ぼすと言わざるを得ません。
そこで民法には、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん) という制度を設けています。
遺留分が保障される相続人の範囲は、配偶者、子、父母であり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分として請求できるのは、配偶者と子が、相続財産の2分の1、また法定相続人が被相続人の親だけの場合は、相続財産の3分の1の範囲です。
ただ、この相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは各相続人の自由意思に任されていて、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害しているとされた者(受遺者や特別受益者等)は、侵害しているとされる遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還する必要があり、その返還する額をめぐって争いになる事例が数多く見受けられます。
そこで、このような争いや訴訟を未然に防止するためにも、遺留分を考慮した遺言を作成することが重要と言えます。
また、遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間と言う短期間の消滅時効にかかります。
また、相続開始から10年間を経過し後に相続があったことを知り、また、その時点で減殺すべき贈与や遺贈があったことを知っても、相続開始から10年以上経過しているので、遺留分減殺請求権の行使はできません。